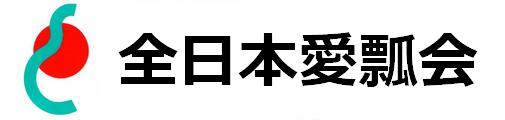特定非営利活動法人全日本愛瓢会の創立50周年記念式典
秋篠宮皇嗣殿下お言葉
令和7年6月12日(木)
本日、特定非営利活動法人全日本愛瓢会の創立50周年記念式典が開催され、会員の皆様とともにお祝いできますことを大変嬉しく思います。そして、この50年という歩みに深い感慨をおぼえます。
私はかれこれ50年余にわたってヒョウタンに関心を抱いております。最初に栽培を試みたのは、小学校低学年の頃です。何故かと問われれば、おそらく多くのヒョウタン愛好家と同様に、その形状に興味をもったということだと思います。しかし、年を経るにつれ、広く世界を見渡すと、その形や大きさが実に多様であることを知るようになるとともに、ヒョウタンの用途が多岐にわたっていることにも関心をもちました。
また、全日本愛瓢会とは、1998年に神奈川県大井町で開催された展示会を視察したのが最初の縁えにしとなります。その後、名誉顧問を経て本会が特定非営利活動法人になった機会に名誉総裁に就任いたしました。爾来、COVID-19の期間を除いて毎年展示会を見学し、会員の素晴らしい作品を堪能しております。
そのヒョウタンですが、皆さまもご存知のとおり、起源はアフリカと考えられており、世界中に伝播したもっとも古い栽培植物のひとつです。日本にも古い時代に伝えられ、滋賀県粟津湖底遺跡など縄文時代早期の遺跡から果皮や種子が出土しております。このように古くから世界の各地で栽培されているヒョウタンは、先ほど申しましたように、その姿形や大きさ、また、器や漁具、装身具などの利用方法が200以上にのぼるなど、実に多様です。また、インドのシタールやアフリカのマリンバなどの共鳴を司っている部分にもヒョウタンが用いられるなど、楽器の要としても用いられています。
これらのことからも、ヒョウタンがいかに人と深く関わってきたかということがよくわかります。そして、これほど多様性を有する栽培植物は稀な存在と言ってよいかと思います。
さて、全日本愛瓢会の事績を振り返ってみますと、まずあげることができるのが、展示会において、毎年のように新たな技法によって装飾されたヒョウタンが出展されていることです。これは、会員の皆さまの熱意によるものですが、今までにない技法を見るたびに感銘を受けております。
またヒョウタンは、小学校における教材としても用いられています。播種をしてから収穫するまでの栽培とその後に行う加工など、小学生にとって有用な教材たり得るヒョウタンを用いた授業には、本会の会員の方々が携わっておられると伺っております。本日見せていただいた福井県勝山市立鹿谷小学校の恐竜ヒョウタンもその一例と申せましょう。
もう一つあげるとすると、育種の結果によって、ヒョウタンの大きさには他の栽培植物に類を見ないほどの潜在性があることを、交配と栽培によって示すことができたことかと思います。たとえば、日本には古くから「日本大瓢」や「長瓢」が存在しております。その大瓢にはアフリカ起源の品種を、長瓢にはアメリカ起源の品種を交配して品種を固定したところ、大瓢は約3倍の容積の「大瓢エース」が、そして長瓢は1.75倍ほどの「スーパー長瓢」が作出されました。これらの品種ができる過程においては、森義夫顧問による育種と会員各位の栽培の工夫が大きく寄与していることは言を俟ちません。そして、わずか10数年の間でこのような育種がなされた植物を私は他に存じません。
この希有な栽培植物であるヒョウタンとその文化の発展について、一言述べさせていただきたく思います。今までにも申し上げてきましたが、これには4つの視点があると思われます。すなわち、人との関係における民俗としてのヒョウタン、育種によって多様に変化する生物としてのヒョウタン、さまざまな工夫を凝らすことができる芸術の素材としてのヒョウタン、そして学校等の教育の現場におけるヒョウタンです。まだ他にもあるかと思いますが、ぜひ多様な側面をもつヒョウタンを考究する役割を本会が持ち続けていくことを希望いたします。
おわりに、全日本愛瓢会が、さらなる発展をしていくことを祈念し、50周年記念式典に寄せる言葉といたします。